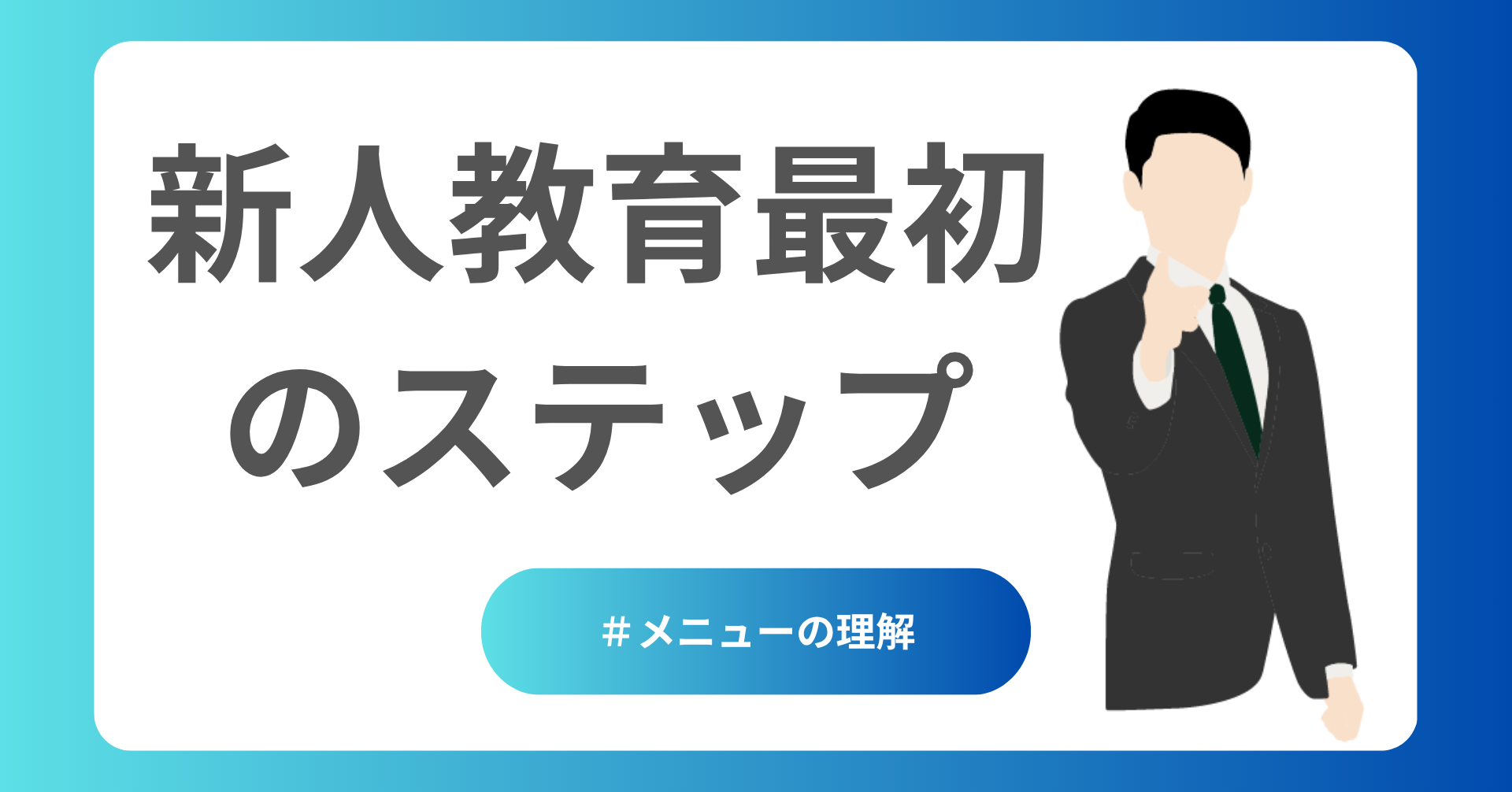メニュー内の専門用語
私が携わってきた飲食業種は、概ね西洋料理でした。
特にイタリアン業界が長かったのですが、
昔と比べてイタリア料理に関しては料理用語が認知されており、
「言葉の壁」が減ってきているように思います。
例えば、カプレーゼ、ボロネーゼ、ジェノベーゼ・・・
“~ ーゼ”というのは、基本イタリアの土地名称から来る郷土料理ですが、
日本では土地の名称よりも、アイテムとして認知されていると思います。
新人の専門用語認知度はどれくらいなのか?
しかし、新人の育ってきた環境はそれぞれで、知らない言葉があるのは致し方ありません。
「これくらいは当然知っているだろう」
は、通じないという前提で考えるべきです。
実際、海外(オーストラリア)のイタリアンにワーキングホリデーで働いていた若者で、
「ジェノベーゼ」を知らなかった例もありました。
ですので、一番最初のオリエンテーションで、私が行っていたことは、
メニューを最初から最後まで一通り見させて、
「分からない言葉を全て書き出して」
と伝えていました。
付け加えて、
「あなたが分からない言葉は、お客様も分からない可能性が高いから」
という理由を添えて。
9割はやらないこと
今の時代は、以下は難しいのでお奨めはしませんが、
オリエンテーション中にその言葉を書き出させて、
分からない言葉の一覧が出来たら、
「次回出勤までに、分からない言葉を調べて」
と伝えるようにしていました。
なぜなら、現場に立つ以上、お客様からすれば、
全員一律でプロであるという認識でいるからです。
ですが、伝えたこちらとしても、完全に覚えられるとも思っていませんし、
また、きちんと調べてくる人もごくわずかです。
そのわずかな人たちは、学ぶ姿勢を持っているので、
正直に言えば、良い意味で「えこひいき」して育てる人に、私は分類していました。
著しく成長が早いからですね。
体感ですが、「えこひいき」する人は1割くらいでした。
4割は「何もせずに出勤」します。
他の5割は「調べたけど覚えられていない」という人たちです。
他にも覚えることが多いので、(例:テーブル番号やスタッフの名前など)キャパシティ的に無理な人もいます。
今は、時間外に何か仕事に関わることを強要することはできませんので、
次回出勤時に、現場で店のWi-Fiを使用させて、勤務時間内に自分でググらせる。
という形が望ましく、実際に今はそうしています。
そういう土壌が良いかどうかはオーナー、店長の考え方によると思いますが、
一つのやり方として、「自分で調べたほうが、覚えやすい」というのは経験則としてあります。
人によっては、耳で聞いた方が覚えやすい。という経験値を持っている人もいますので、
自覚している人には、教えて育てるという手法も必要かと思います。
相手のレベルによって、やり方を変える必要があるという事ですね。

接客レベルに紐づく「知識」
私が飲食業界に入った際に教えられた一つに、
「知識のない奴に物は売れない」でした。
ですので、自然と学習しましたし、
人の説明を盗み聞きして自分の説明に反映させたりなど、
まぁ、普通のことをやっていました。
しかし逆を言えば、自習せずとも現場に立つ人もいます。
そういった人たちは、自然とお客様を避けるようになっていきます。
聞かれる、知識が無いことがバレるのが嫌だからですね。
それがひいては、接客力が不足していくことに繋がっていきます。
でもそれは、店長がそれを放置している――
という背景もありますので、一概にスタッフだけを責めれません。
知識は自信
新人スタッフに何より必要なのは、
必要とされていると自覚させることです。
すなわち、「存在価値」を認めてあげること。
そのために、まずその職場に必要とされる、
戦力として認めて貰えるように導いていくことです。
飲食店でのスタッフの存在価値は、店それぞれで違うと思います。
が、根本的に提供している商品を知らない人がいることは、
お店にとって、マイナスでしかありません。
その知識を基に、経験を育み、そしてお客様の喜びにつなげていく―――
新人が覚えるべきは、まず会社・お店の基本的な考え方と、
「商品知識」であると、私は考えています。
私共では飲食店スタッフ教育のための
「入社時の研修項目」を共に創るサービスも行っています。
ご興味があれば、お話だけでも聞かせて下さい。